板垣啓四郎
FAOが出版している“The State of Food Security and Nutrition in the World 2024”「世界の食料安全保障と栄養の現状2024」によれば、2023年で世界人口のおよそ7億3,300人が飢餓に直面している可能性があると推定されている。地域別にみると、アフリカが依然として飢餓に直面している人口の割合が大きい地域とされており、その値は20.4%(アジア地域8.1%、ラテンアメリカ・カリブ海地域6.2%)、実数で3億8,500万人と推定されている。また中程度ないしは重度の食料不安を抱えている人口は世界人口の28.9%(23億3,000万人)であり、地域別にみるとアフリカが地域人口に占める割合で58%にも達する。食料不安は男性よりも女性に、都市部よりも農村部のほうがその割合がやや高い。加えて少なくない人数の子供たちが飢餓や食料不安に直面している。今後とも人口の増加とともに食料不安の人口は増加していくものと予想され、栄養問題は重要なグローバルイシューであり続けるであろう。
3月27・28日の2日間にわたり、パリでNutrition for Growth Summit(成長のための栄養サミット、以下N4G Parisと略す)が開催され、それに出席した。N4G Parisはメインのアジェンダに加え、数多くのサイドイベント、そしてVillages of Solutionsと称したパネルセッションでもって構成された。N4Gは、政府、国際機関、研究機関、慈善団体、市民社会組織、民間企業などが世界および地域のレベルで結集して、栄養を持続可能な開発アジェンダの中心におき、あらゆる形態の普遍的な栄養不良の原因を明らかにし、4年ごとに開催されるN4Gサミットの継続性を確保して栄養状態を良好なものにするためにさまざまな角度からコミットメントし、栄養不良からの進展を加速させるというものである。

前回は2021年12月に東京で栄養サミット2021が開催、そこで東京栄養宣言(グローバルな成長のための栄養に関する東京コンパクト)が発出された。東京栄養宣言では、2030年までに栄養不良を終わらせるため、健康・食・強靱性・説明責任・財源確保という5つの項目について、今後取り組むべき具体的な方向性が示された。またイノベーションを通じた食料システムの変革により食関連産業が栄養改善に貢献、食育等により個人の行動変容が促され、また政府と企業の連携により途上国を支援していく旨が述べられた。
N4G Parisでは、この東京栄養宣言を引き継ぐ形で、メインのアジェンダでは、政府、国際機関などのマルチステークホルダーが、栄養の成果を持続発展させるための効果的な戦略を事前に設定された6つのテーマに基づいて協議するとともに、その結果を踏まえて成長のための栄養(N4G)に向けたビジョン、ロードマップおよびコミットメントを策定することに主眼がおかれた。設定されたテーマは、①栄養、健康、社会的保護、②気候変動対応型で回復力のある持続可能な食料システムへの移行、③栄養と危機へのレジリエンス、④栄養とジェンダー平等、⑤データ、研究、人工知能(AI)、栄養のためのイノベーション、➅栄養に関する資金調達と説明責任、である。
サイドイベントでは、さまざまなテーマのもとに活発な議論が展開された。それらを逐一紹介できないが、テーマをカテゴリー別に仕訳けすると、おおよそ以下のように分類できる。栄養改善に取り組むうえで、①様々な部門の有機的結合、②資金供給メカニズムの構築と活性化およびアカウンタビリティ、③関係するデータ・情報の収集/集積とその分析および活用、④民間セクターの積極的介入と資源の有効活用、⑤女性のエンパワーメント、➅学校給食プログラムのインパクトであり、また栄養改善に考慮すべき点として、⑦持続可能な開発とフードシステムの転移、⑧フードシステムと気候変動、などが挙げられている。
かかるカテゴリーのなかで、特に注目された議論の一つに学校給食を取り上げることができる。学校給食は栄養と開発の主要な推進力であり、国連総会においても、学校給食は栄養と教育および児童の成長を促すうえで決定的に重要なプラットフォームであり、地球上の飢餓と栄養不良を終結させる中心的な役割を果たすとした。学校給食は、就学児に対して健康的な食品へのアクセスを増やすことができ、栄養の量と質の向上、栄養素のバランスの維持が期待され、その結果として子供たちの健康が増進し疾病が抑制される効果をもつ。実際、FAOの資料によれば、学校給食は低・中所得国を中心に4億1,800万人の児童に恩恵をもたらすとされている。とはいえ、学校給食を立ち上げるには多くの課題が存在する。学校給食の政策指針・行動計画の策定およびそれを裏づける法律の制定、地域住民に対する学校給食の理解と啓蒙、十分な予算の確保、給食施設の設置、栄養プログラムの構築と実現可能な献立の組み立て、栄養士など栄養の普及と教育に携わる人材の養成、児童や家族に対する食育と栄養の指導、衛生に対するAwarenessの醸成、切れ目のない食材と在庫の安定確保、学校給食の効果を測定するためのデータの入手とその分析など、やるべきことが山ほどある。国によっては、宗教、食文化、ジェンダーなどの違いによって、給食のあり方も多様である。予算と人材が十分でない低・中所得国において学校給食を手掛けるには、あまりにもハードルが高い。国際機関や慈善団体、民間の力を借りることがどうしても必要である。
Villages of Solutionsでは、政府、国際機関、研究機関、慈善団体、市民社会組織、民間企業から、栄養改善に向けた具体的な活動が紹介された。数多いパネルの中から、ここではGRET、World Vision International in Vietnamなどの慈善団体およびIRRI、ICRISATなどCGIAR傘下の研究機関の取り組みについて若干触れることにする。GRETは、サハラ以南アフリカ諸国を中心にして、過去30年間にわたり、低栄養、微量栄養素の不足、過体重など、貧困と低開発が原因となり結果となる悪循環を断ち切るために、食事と健康管理の改善を通じてあらゆる形態の栄養不良の防止に取り組んできた。GRETの活動の特徴は、対象となる国や地方において、政府、民間企業、コミュニティなどと連携して、推奨する食品の普及と栄養の摂取、健康管理のあり方を実践していくという点にある。World Vision International in Vietnamは、ベトナムの遠隔・山岳地帯を対象にして、健康増進と栄養改善に関するプログラムを実施しており、長期を見据えコミュニティを基礎にした総合的アプローチ、すなわち住民の健康の回復、農業と経済開発、乳幼児の世話、清浄な水の確保と衛生管理、マイクロファイナンスなどを一体的に取り組んでいる。特に2023-27年では、5歳未満児の感染症と疾病の削減を目標とした「健康と栄養の技術プログラム」を実施している。IRRIは食後血糖値の上昇を大幅に抑えまた品質のよい高タンパクのコメ品種を作出し、コメを主食とする糖尿病患者に対して大きな恩恵を与えている。またICRISATは、アフリカ、アジアの低所得世帯で毎日の主食となるミレットに鉄分を多く含んだ新しい品種を作出して普及し、女性や子供が苦しんでいる貧血を軽減していくことが期待されている。アフリカではこの研究が最初の栄養強化ミレットとして注目されている。
N4G Parisは、最終的に以下のようなコミットメントを発出した。持続可能なフードシステムに向けた移行の過程を強化し、栄養に富んだ食事に誰しもが均等にアクセスできるよう促すこと、特に女性が栄養改善と持続的な開発の中心となるよう能力を強化してだれ一人取り残さないようにすること、人々を健康に導くシステムを強化してレジリエンスの高いものにし社会的な保護システムを強めていくこと、栄養改善上の数々の成果を環境や気候を含めた広範なセクターにつなげていくこと、などである。またエビデンスベースの政策を優先、資金へのコミットメントを増加、セクター間の連携を強化することにより、栄養不良の改善に向けた進展がさらに意義深いものとなっていくようにすることが唱えられた(Final Statement of the Nutrition for Growth Summit)。
以上、N4G Parisの概要について述べてきたが、今回のサミット参加は栄養改善の重要性について深く考える機会となった。このサミットでは、持続可能な栄養政策の導入と強化、そしてそれが世界的規模で健康と福祉にどのように寄与するかについての議論が活発に行われたが、特に子供たちの栄養改善の必要性とそれに伴う社会的、経済的影響について多くの知見と洞察が得られた。栄養状態を改善して人々の健康が回復し維持され続けることは経済開発を推進していくうえで避けて通れず、また人としての尊厳性を高めるうえでもきわめて重要である。

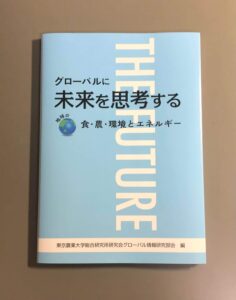
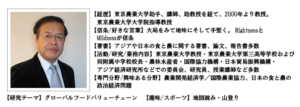
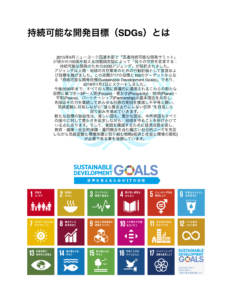
Comment