GIAスポーツ考察
Let’s Play ball!! 日本での野球発展の歴史(黎明期)
日本人のスポーツ好きは世界中に知られています。
まず国技は『相撲』。とは言うものの一般の我々にとって大相撲(プロ)は全くの観戦スポーツ、NHKでのTV観戦はまだしも、実際の生観戦は一生に一度の夢、と言う人も多いのではないでしょうか?強豪である我が東京農大を含めた学生/アマチュア競技としてはそれぞれの団体が統括し、地方などでも様々な大会が開催されますが、性別もほぼ限定される競技でもあり観戦スポーツとしての位置づけが強いようです。
国際的な競技に目を向けると4年に一度開催されるオリンピックへの注目度は非常に高いです。フジヤマのトビウオ(水泳)、東洋の魔女(女子バレー)、日の丸飛行隊(スキージャンプ)など、戦後日本の復興を象徴するかのように高度経済成長に合わせたアスリート達の大活躍。近年はお家芸と言われる体操や柔道、各種スケート競技やバトミントン、カーリングやスケートボードなど新競技での躍進。性別、夏季・冬季、個人・団体を問わず様々なヒーローやヒロインが登場し、今やニュースやCM出演、テレビバラエティ番組のメインゲストとして招かれることも少なくありません。オリンピックからの広がりとしてパラリンピックや耳の聞こえないアスリートが集うデフリンピックなども開催され、全ての人がスポーツを楽しめる環境が進んでいます。
そんな数々の注目の各種スポーツ界にあって、一昔前の『巨人・大鵬・卵焼き』から引き継がれ、相撲に並ぶ日本の国民的スポーツと言えば『野球』。そして近年集まるMLB(大リーグ)人気を見るにつれ、今まさに野球を語らない訳には行きません。
●Baseball(英語)=野球(日本語)=棒球(中国語)=ヤギュ(韓国語):
アメリカで1800年代半ばに誕生したベースボールは、その後の南北戦争の終わりと共に全米各地に浸透し、1869年(明治2年)に最古のプロチーム、シンシナティ・レッドソックスが誕生しました。現在のシンシナティ・レッズの前身(2021年に秋山翔吾選手が在籍)チームです。その後、興行としてのプロリーグやプロチームは全米に数々誕生し、人種分離政策のあった1920年当時には今だに最強と言われるアフリカ系アメリカ人のみによるプロ野球リーグであるニグロ・リーグも存在していました。皆さんご存じのMLB初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンも第二次世界大戦後のニグロ・リーグ出身。その後ドジャーズ傘下のカナダのチームを経由、1947年にメジャーリーグのブルックリン・ドジャーズ出場を機にプロチームでの人種融合も進み、長い年月を経て現在に至っています。
アメリカではベースボールを『America’s Pastime=アメリカ全国民の娯楽』と表現し、老若男女が楽しめるひと時として伝統となっています。応援も日本のような勤務後にナイターに繰り出し、応援団を組織してラッパや太鼓を吹き鳴らし応援歌を声をからして大合唱すると言うスタイルでは無く、日中の青空と白い雲を眺めつつ球場に流れるのんびりとしたオルガンの音の下、ホットドッグとコーラを片手に、おじいさんが孫にスコアブックの付け方を教える、と言うようなほっこりとしたファミリーの時間帯でもあります。実際に、1881年設立で緑のツタが覆う外野フェンスが有名な名門シカゴ・カブスのリグリーーフィールドでは長年に渡りデーゲームしか行われず、ナイトゲーム(日本語ナイター)が開催されたのは何と1988年の事でした。
●日本での国民的スポーツ『ベースボール➡野球鬼ごっこ➡野球』が育った黎明期(明治時代):
さて目を日本に転じると明治5年(1872年)にアメリカ人牧師のH・ウィルソンが東京の生徒たち(東京大学の前身)にベースボールを伝え競技が始まりました。当時は「打球おにごっこ」名称で全国に広まったと言われています。
その後、明治11年(1878年)に、機関車両技師としてアメリカ留学から帰国し、現在では日本野球の祖と呼ばれる平岡凞(ひらおか・ひろし)が新橋アスレチック倶楽部を設立、ここに日本初の組織としてのベースボールチームが誕生しました。その後、明治15年(1882年)には新橋アスレチック倶楽部と駒場農学校(後の帝国大学農科大学)が日本初の対抗試合を実施。
興味深いのは当時の野球の広がりは学びの場(大学)を中心にアメリカ人教師(多くの場合牧師だった)やミッション系大学群、またアメリカからの帰国日本人達が担ったという点で、設立が早かったのはアメリカ人英語教師がいた開拓使仮学校(後の札幌農学校))や 東京英和学校(後の青山学院大)、工部大学校(後に東大に合併)、立教大学校(後の立教大)、波羅大学(後の明治学院大)、明治21年(1888年)には三田ベースボール倶楽部(後の慶応大)野球部が創部。このようにアメリカ人教師やアメリカ経験のある日本人達が盛んにベースボールを伝える中で明治27年(1894年)には中馬庚(ちゅうま・かなえ)によりベースボールが初めて『野球』と日本語訳され、明治30年(1897年)には野球研究書「野球」を著作。これは日本初の野球解説専門書で、この書籍を以てしてベースボールとして伝わった『野球』は日本の国民的スポーツとして発展する基盤を築きました。
●1910年(明治43年)東京高等農学校(後の東京農業大)の野球部が創部!!
我が東京農大は日本の中でわずか数校しかベースボールチームが存在しない驚くべき早い時期、なんと明治43年(1910年)に野球部が設立されました。
これは私が個人的に想像するに、農大が明治期の日本に於いて国家を担う重要かつ先進的な知識を得られる学び舎であったと共に、学風は自由闊達、学生・教員共に先進性に熱意に溢れていたのだと実感します。また、農大の基礎が徳川育英会であったのも当時の政界や財界はじめ様々な人的ネットワークの中心であった事、そこで国内外からの最新情報を得られる優位な環境だったと推測します。ちなみに、慶応大学野球部前身の三田ベースボール倶楽部も徳川家と関係が深く、前述の日本野球の祖と呼ばれる平岡氏は田安徳川家の当主・徳川達孝に英語を指導した記録があり、田安邸跡は現在の慶應義塾女子高等学校の敷地です。
ちなみに、東京農大が大学対抗スポーツの華、箱根駅伝に出場するのは野球部設立約10年後の1921年の事です。こう考えると東京農大の野球部は日本の野球文化をその黎明期から支えてきた重要なチームでもあります。
我が農大野球部創設の数年後の明治45年夏に明治天皇が崩御され年号は大正に代わりますが、当時の野球人気は大学がけん引しました。こうした流れは大正4年(1915年)全国中等学校優勝野球大会(現在の夏の甲子園大会)の開催に繋がり、更にそのすそ野を広げることになりました。
●日本人の野球好きを決定づけた東京六大学:
東京六大学野球連盟は、早稲田・慶應義塾・明治・法政・東京・立教 の6つの大学で構成される野球リーグです。その歴史は大正14年(1925年)9月20日の明大対立大第1回戦を連盟創設初試合として、明治36年(1903年)に第1回の早慶戦、大正3年(1914年)に早慶明の三大学によって初めてリーグ戦が組織されました。次ぐ大正6年(1917年)に法政、大正10年(1921年)以降にに立教大や東大が加入し六大学リーグ戦が開始されました。
面白いのは大正15年(1926年)には東京六大学野球連盟の協力のもと、明治神宮野球場が建造されたと言う事です。大学野球と神宮球場とは切っても切れない縁があるのですね。
さて、ここまで日本での野球の伝達と発展黎明期を記してきましたが、時代的にはまだ大正時代。職業野球としてのプロチームの誕生はまだまだ後のこと、第一次世界大戦終了、関東大震災や世界大恐慌を経た昭和9年11月(1934年)、ベーブ・ルースを含む大リーク選抜チームの日本遠征まで待たないとなりません。
-1989年卒 鎌塚俊徳





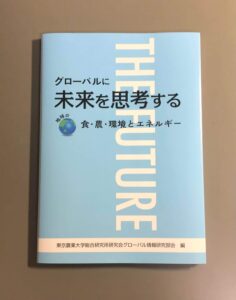
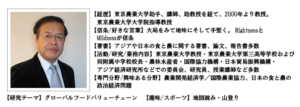
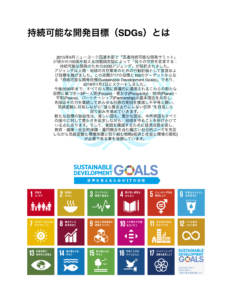
Comment