1、はじめに
アメリカの農場数は、第二次世界大戦以降速度を緩めながらも減少をつづけています。
一方で小規模な農場が吸収・合併された結果、 平均農場面積は拡大傾向が継続しています。
1997年の総農家数は206万戸、 平均農場面積は188ヘクタールに及びます(第1図)。 
日本の農家の100倍以上の平均農場面積にもかかわらず、
アメリカの家族農業の経営は決して楽ではありません。
多くの農家が農業収入のみでは生計が成り立たず、
農場外の収入に依存しながら生き残りをはかっています。
その一方で、企業が経営する大規模農場は着々と利潤を上げ、ますます巨大化しています。
アメリカ政府は数十年にわたり一貫して規模拡大を奨励し、
大規模農場に有利な政策を採用してきました。
ところがようやく最近になって、
アメリカ農務省がこれまで政策上まったく顧みられなかった小規模農場の見直しを始めました。
大規模農場優遇政策がアメリカの農業にいかなる影響を及ぼしてきたのか。
なぜここに来て小規模農場を支援する動きがはじまったのか。
ここでは、1998年1月にアメリカ農務省の小規模農場に関する委員会が提出した
「行動の時」と題するレポートに焦点を当てながら、その背景と意義を探ってみたいと思います。
2.小規模農場を救え-小規模農場に関する委員会レポート「行動の時」-
■ 2-1「選択の時」から「行動の時」へ
1970 年代のアメリカは、ニクソン政権による農産物輸出拡大政策の下、
東欧諸国や開発途上国での需要増大に対して、
作付面積の拡大と化学肥料や農薬(特に除草剤)の多量施用、
灌漑設備の拡充などによる増産で応え、未曾有の穀物輸出高を達成しました。
1970年には4100 万トンに過ぎなかった穀物輸出量が、80年には1億1300万トンと、
わずか10年間に2.8倍に増加して、全世界の穀物輸出量に対するアメリカのシェアは
35.2%(70年)から50.6%(80年)に急上昇したのです。
そうしたアメリカ農業の近代化路線に対して最初に警告を発したのは、
カーター政権(1977-1981)の農務長官ボブ・バーグランドでした。
ミネソタ州の農家出身で現場と農政のギャップを痛感していたバーグランド長官は、
1年半をかけてアメリカ農業が抱える構造的な問題とその解決策に関する実証的研究を行い、
政権交代を目前に控えた1981年1月「選択の時」と題するレポートを公表しました。
彼はそのレポートで、化学物質や石油に依存しきった慣行農法により、
構造的な生産力の低下が生じていること、
大規模な農場に利潤が集中する偏った利益構造が存在すること、
農業には規模の利益が乏しいのみならず、
農業生産では大規模化がもたらす経営採算上のメリットが乏しいこと等を指摘して、
規模拡大を助長している農政の抜本的転換を訴えました。
80年代には、農業経営をめぐる内外の経済的環境が悪化の一途をたどりはじめたため、
農家や農業関係者の間にこれらの諸問題を根本的に解決できる農法に対する期待が高まり、
有機農業や代替農業に関する調査結果が続々と報告されます。
さらに持続的農業を重視した多くの法案を含む1985年農業法と1990年農業法の制定により、
アメリカの農政転換はますます本格化しました。
しかし、以上の経緯を綿密に調査された中村耕三氏は次のように述べています。
「数十年間にわたって『化学物質偏重の近代化農政』が吹きすさぶなかで、
この国の農業再生にとって不可欠な『持続型農業』を堅持して培いつづけてきたのは、
企業的な大規模経営でもなければ、巨大アグリビジネスでもなかった。
それは、この国の政治を建国以来支えてきた民主主義的理念のルーツたる
農村社会の担い手でもある『家族農場』
(家族労働を主体とする自立的農業経営)にほかならなかった。」
「しかしながら、バーグランド元農務長官が『選択の時』報告の序文の中で喝破したように、
この国の政治が過去数十年来『農業にもスケール・メリットが存在する』かの幻想に支えられて、
すべての面で大規模経営を偏重する方向で推し進められてきたことが大きく影響して、
最近では『家族農場』の農業からの離脱や挙家離村が急速に進んでいる。」
私(筆者)は『アメリカの農政転換』が最終的に成功を収め得るか否かは、
それが『大規模経営を偏重する農政からの決別』にまで
発展し得るか否かにかかっているといっても、決して過言ではないと思っています。
その大規模経営偏重農政の見直しは、
1998年1月にアメリカ農務省の小規模農場に関する委員会によって公表された
「行動の時」と題するレポートによって、ようやく開始されました。
このレポートの作成に至った経緯は次のとおりです。
1997年2月アメリカ農務省内の公民権アクションチームが
「人種差別に加えて、政府の政策と慣行が小規模農場の農家を差別してきた」ことを認め、
農務長官に小規模農場に関する委員会の設置を勧告しました。
これを受け1997年7月ダン・グリックマン農務長官(当時)は
「アメリカの小規模農場の現状を調査し、アメリカ農務省が小規模農場のニーズを認識し、
尊重し、それに答える一連の行動を策定する」ため、
小規模農場、金融、通商、農村社会、非営利団体、学会、州および地方政府、
アメリカ原住民、農場労働者などの代表30名によって構成される
「小規模農場に関する委員会」を召集します。
委員会は全米各地で公聴会を開催し、 そこで得られた200名からの口頭証言、165の書面証言、
そして委員会のメ ンバー達の経験に基づいて、
委員会の設立から半年後の1998年1月にレポート「行動の時」を公表しました。
■ 2-2 小規模農場見直しの背景
+ 2-2-1 「選択の時」以降の農政
「バーグランド元農務長官のレポート『選択の時』は
『現行の政策と事業が 規模拡大の情勢を強化促進するのでなく、
それを阻止する方向に転換しないかぎり、 数年のうちに、
ごく少数の巨大農場が食糧生産全体を支配することになるだろう』と警告を発した。
以来20年後の現在顧みて、この警告が留意されなかったばかりか、
それ以降なされた政策選択が資産と富を大規模農場と巨大なアグリビジネス企業に
一層集中させる構造的な偏りを犯してきたことは明らかである。 (太文字筆者)
今日では1979年に比較して、農場数は30万件減少し、
農家の収入は消費者価格1ドルあたり13%少なくなった。
いまや4件の企業が肉牛市場の80%以上を支配している。
わが国の農場の約94%は小規模農場であるが、その収入は全農場収入の41%に過ぎない。」
なお本レポートは、小規模農場を 「年間粗収入が25万ドル未満で、
日常の労働と管理を農民個人または農民とその家族が行い、
かつ生産物を所有あるいは生産資産を所有ないし賃貸する農家」と定義しています。
ここでいう「農場」は作物を栽培する農場のみならず畜産・酪農牧場をも含むため、
農場の「規模」を「面積」ではなく「年間粗収入」で分類しています。
+ 2-2-2 大規模農場優遇政策と規模の利益
「連邦農場事業に参加している農家はアメリカ全農家の約3分の1であるにせよ、
この事業は歴史的に最も大規模な農場が利益を得るような構造的偏りを持っていた。
農場への支払いが生産物の総量に基づいて計算されてきたため、
大規模農場に多くの割合が支払われ、それが大規模農場のさらなる資本化と経営拡大を可能にした。
税制は大規模農家にさらに農場を拡大するような動機を与えている。
雇用農場労働者に依存する大規模農場は、 連邦労働法の適用免除を受け、
好都合な低賃金労働力を手にしている(写真1)。」

写真1:カリフォルニア州サンタクルーズの有機イチゴ農場で働く移民労働者
半年間ほぼ連日腰を曲げての収穫作業は過酷である。
彼らが最低労働賃金(1995年当時で時給4.25ドル)以上を受け取ることは多くない。
野菜・果樹など収穫の機械化が困難な作物の大規模経営では 賃金の安い移民労働力の存在が欠かせない。
全米随一を誇るカリフォルニア州の野菜・果樹生産は
メキシコからの低賃金農場労働者に支えられている。
ではなぜ大規模優先の政策がとられてきたのか。
「一見すると大規模な農場ほど効率的だという世論があり、
したがって大規模農場に対する国としての関心も高い」、というように受け取れるが、
それは誤りである、として次のように述べています。
「多くの人々が『少数の大規模農場』という事態を経済進歩の必然の結果と考えている。
例えば、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者は最近かなりの確信をもってこう書いた。
『実際、地方の酪農家はもはや必要ない。 巨大農場がニューメキシコやアイダホにできて、
絵葉書のように美しいバーモントの酪農家よりはるかに安く牛乳を生産している。
さらに、加工業者はフィルターで牛乳から水を分離する実験をしている。
これは国を横断する輸送コストを安くする』。

写真2:カリフォルニア州サリナス渓谷でのレタス収穫風景
流通ルートを持つ大規模農場の作業員一行が契約農家の圃場を訪れ収穫していく。
農家は栽培するのみで収穫は行わない。
この圃場の灌漑用地下水は飲料水基準を超える硝酸を含んでいた。
従来の『大規模化、さもなくば離農』式の政策は『経済進展』の本当のコストを認識できない。
この視点は寡占市場において生産が集中した場合の市場競争の喪失を考慮しない。
多数の家畜の限られた区域への集中が環境におよぼす潜在的な結果を考慮しない。
数件の巨大農場を疾病や天災が襲った場合の安定した
牛乳供給といった安全保障に対する危険性を考慮しない。
国を横切って牛乳を輸送する際の化石燃料増加のコストを考えない。
水が抽出された場合の細菌の増加を考慮しない
特に真のコストを考慮した場合、常識とは反対に、
大規模農場は小規模農場よりも効率的に農産物を生産しない。」
さらに、委員会の公開会議の席上、 ピーターソン教授(ミネソタ大学)は
規模以外の要因が農業の単位コストに影響することを見出し
「小規模農家と兼業農家は少なくとも大規模な商業的農場と同様に効率的である。
実際、農場規模の増加にともなう規模の不経済の証拠がある」と明言した、としています。
+ 2-2-3 大規模優先政策のもたらしたもの
「他の主要な産業と同様に、農業資産の所有権と管理はますます少数者の下に集中している。
資本集中は地域レベルで開放された自由市場の喪失を引き起こす。
農家は多くの売り手と少ない買い手からなる市場で取引する。
農民はその生産物の価格決定に対してほとんど、あるいはまったく支配力を持たない。
“自由競争”市場という原則は、今日の作物および家畜市場においてますます認めがたくなっている。」
「『規模の不経済』は農場の柵を越えて農村社会にも影響を及ぼす。
アメリカの土地所有権は多くの場合農業の集中が原因で、 ますます少数の地主に集中されつつある。
カリフォルニア大学の人類学者ディーン・マッカーネルによると、
農場の規模と不在地主の数が増大するにつれて、地方社会の状態は悪化する。
彼らは家庭収入の低下、貧困の上昇、教育の低下、 民族間における社会的・経済的不平等などが
土地所有と農業資本の集中に関連していることを見出した。
家族のみで経営可能な限度を超えた大規模な農場に囲まれた地域社会は、
少数のエリート富裕層と大多数の貧困層という二つのピークを持った収入分布を示した。
地域社会における中間層の欠落は、社会的・商業的活動、公共教育、地方政府などに
質・量双方にわたる深刻な悪影響を及ぼしていた。」
「大規模農業組織が生産方法への資金投資を避け、
リスクと経費の両方を契約農家あるいは社会全般に水質や土壌の汚染、
あるいは農村社会への連邦補助の増加という形で押付けているという指摘が、
記述あるいは口頭証言を通じて繰り返された(写真2)。」
「研究がより多くの資金を要する農業技術の開発に専念し、
ごく少数者だけにわが国の食糧生産を可能にするにつれて、
収入と機会は農場から生産資材を製造・販売する企業へと移動した。
さらに農民が未分化な未加工品の生産にいそしむ間に、
食料システムの利潤と機会は食品加工、包装、販売を行なう企業へ移行した。
その結果、1910年から1990年の間に農民が手にする 農業経済のシェアは21%から5%に激減した(第2図)。」

「食品加工業者間での資本集中の増大、競争市場の喪失、
そして政府の価格支持策の減少が相俟って、農家をますます困難な情況に追い込んでいる。
農家は今後、自分たちの経済的保障に対する自らの支配力をますます失うであろう。」 (太文字筆者)
以上のように、大規模優先政策はアメリカ農業の経済的
(競争的市場の喪失、大規模農場への利益集中、少数の大規模農場による高価な生産手段の独占)、
環境的(利益のみ追求し環境に配慮しない)、
社会的(農村社会の崩壊)側面のそれぞれに深刻なダメージをもたらしてきたといえます。
「第3章 序」は以下のように締めくくられています。
「一度以上の機会で、公聴会で発言した農家が当委員会を『われわれの最後の希望』 と呼んだ。
この国の小規模農場の役割と重要性を減少させない、という『選択』は20年近く前になされた。
ここに確信と希望をもって、小規模農場に関する委員会は議会とアメリカ農務省に対し、
アメリカの小規模農家のニーズのために『行動』することを要求する。」

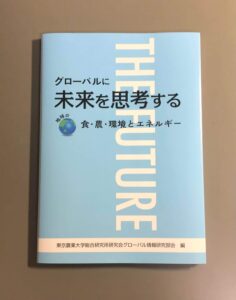
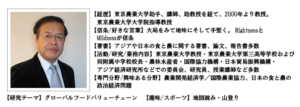
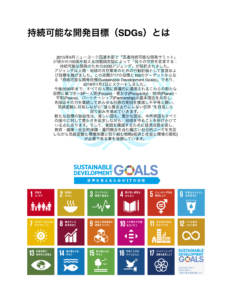
Comment