出所:US Rice Federation
カリフォルニアの水不足は、今年も深刻な事態となっていることが最近も見聞きすることが多い。
各種の報道でも、またアメリカ農務省の公表する指標や
「U.S. Drought Monitor」地図などでも、それはわかる。
例えば下図は、今年8月後半の全米干魃地図であるが、
西海岸を中心に、特にカリフォルニアは「D4」の最高レベルの干魃予想が出されている。
図1 アメリカの干魃地図

出所:USDA, The National Drouht Mitigation Center
カリフォルニアの干魃予想をより詳細に地図に落としたものが図2である。
それによると北はチーコのあたりまで、南はロサンゼルスをこえて、
また内陸部はネバダに至るまでの広範囲に干魃予想が出されているのである。
いわば、カリフォルニアのセントラルバレー全域に深刻な干魃が予想されていると言って良かろう。
ところでこのセントラルバレーは、
カリフォルニアの農業地帯で有り穀物や果樹、野菜等々の生産の中心地帯でもある。
特にその北部(サクラメントバレー)では、
TPPの関係で喧伝されている日本向けアメリカ米の生産地として名高い。
アメリカの中粒種米の主要生産地帯である。
この水不足傾向は、昨年も同様で、
二年続きの「大干魃」にカリフォルニアは見舞われていることになる。
いや、カリフォルニア農業の場合、恒常的に水不足の問題は大きな課題で有り、
労働力の確保問題と共にカリフォルニア農業の二大課題であるといってもよい。
図2 カリフォルニアの干魃地図
U.S. Drought Monitor,2015
California

出所:図1と同じ
アメリカから日本に輸出されている中粒種米のほぼすべてが、
コルサ郡やグレン郡などのセントラルバレー北部(サクラメントバレー)で生産されている。
つまり、日本の米市場を巡るTPP交渉、
特に日米交渉のアメリカ側の主生産地がこの北部セントラルバレーなのである。
図3カリフォルニアの米地帯

出所:California Rice Council
その地域で、さきのような大干魃が予想され、また実際に干魃が起こっている。
その原因については、全体的な温暖化や地下水の過剰利用による水位異常低下、
ネバダ山脈の降水量の減少等々、各種の分析があるが、
いずれにしろ日本農業、稲作と関わりが深くまた深くなるであろう事が予想される
カリフォルニアの北部セントラルバレーで深刻な水不足が発生している。
カリフォルニア農業の中でも米栽培は、
農産物中最も水利用量が多い作物の一つであることは言うをまたないが、
そのカリフォルニア米の主要産地で、深刻な水不足が起こっており、
当然のことながら水不足、確保できる水の減少により生産量の減少が生じている。
例えば2013年比の2014年のカリフォルニア中粒種収穫面積は23㌫減、
生産量は22㌫減となっていた。
そして2015年は2014年比30~40㌫の作付面積の減少も予想されていた。
このようなカリフォルニア稲作の水不足状況の中で、
当然、その価格も高騰するはずであった。
確かに2014年は、平年を大きく上回る価格水準が示され、
干魃による生産量減少が米不足につながり、それが価格を押し上げ、
100ポンドあたりの精米所引き渡し価格で平年を7~8ドルも上回ったのであった。
ところが、2014年に続く2年連続の干魃に襲われた2015年の米価格は、
表1のように、高水準とはいえ中粒種で昨年より2~5ドル、10㌫程下回っている。
水不足と生産量減少の結果、高価格の持続が予想されるにもかかわらず、
2015年は当初からジリジリと値下がりしているのである。
2015年8月31日でも昨年同期の水準を回復していない。
一方、価格決定の一因である消費量の大幅な落ち込みも聞いていない。
アメリカでも、特に日本人や極東アジア人の多いカリフォルニアでは、
日本食ブームはいまだ続いているし、消費はむしろ堅調といえるのではあるまいか。
では依然高水準とはいえ2014年に比した価格低下の要因はどこにあるのか。
いくつかの要因が考えられるが、昨年の高水準価格が米不足を見込んだ投機的価格であり
(実際、表1に見られるように、昨年1月~4月の価格上昇は異常ともいえるものであった)、
その反動が今年の米価に現れているとか、実消費そのものが低迷し始めているとか、
昨年の蔵米が放出され始めたとか、いくつかの要因が考えられるが、
しかし実態は不明なことが多い。
こう考えると、私たちは日本への最大の米輸出地域になるであろう
カリフォルニアの米需給動向の不安定性に懸念を持つと共に、
マスコミ等で喧伝される「100年に一度のカリフォルニア大干魃」下での
カリフォルニア米生産や価格への影響も、慎重に考える必要があるであろう。

出所:筆者撮影
東京農大 立岩 寿一
補足


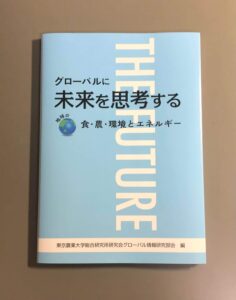
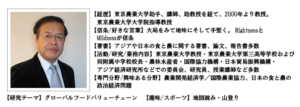
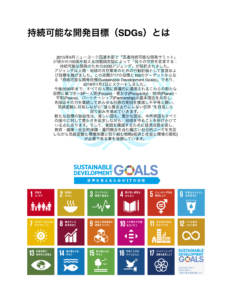
Comment